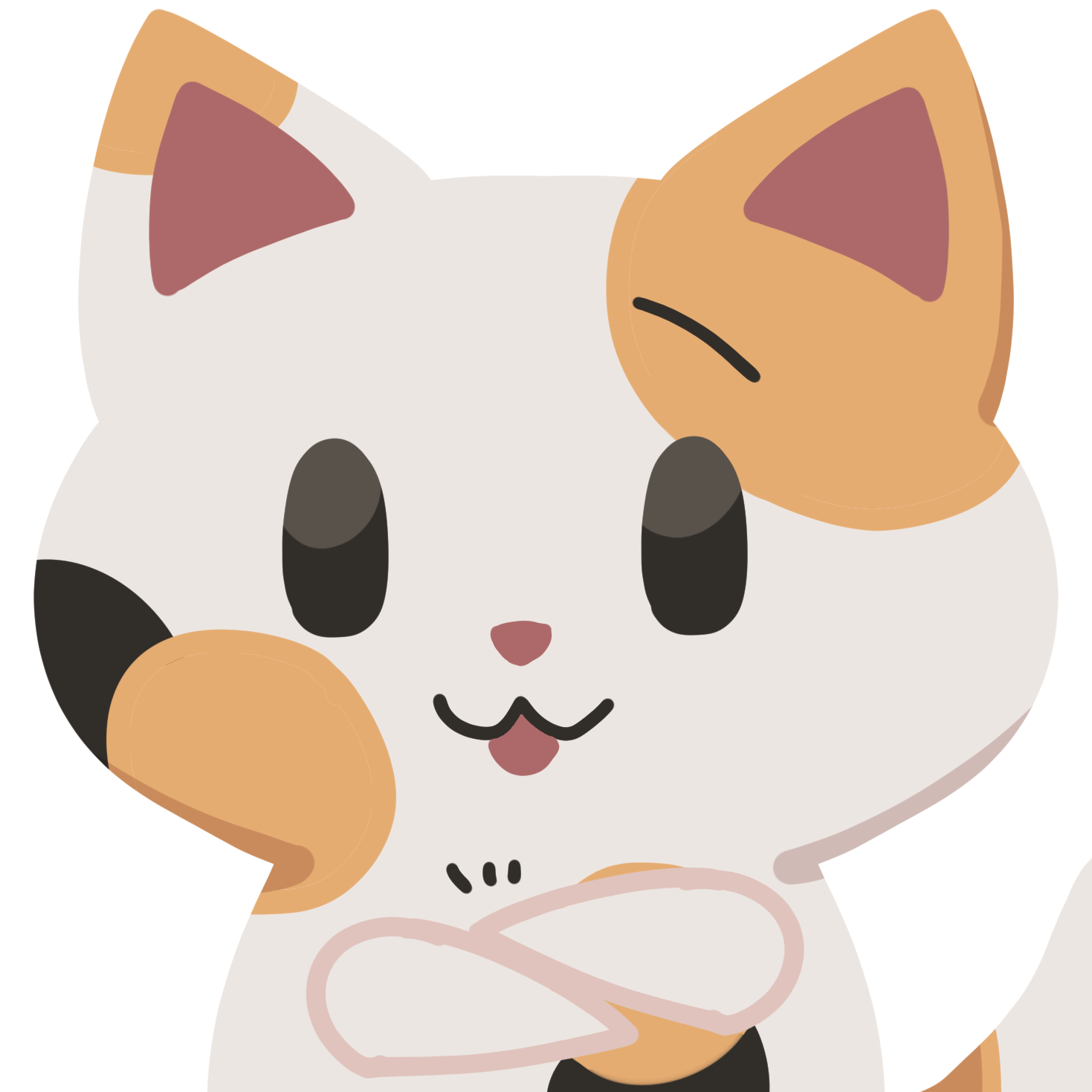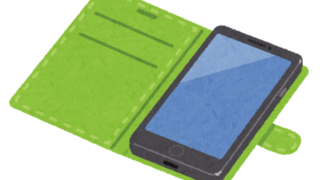通勤定期券をお得に買う方法とは?1ヶ月で何日利用すると得なのか含めて徹底解説!

- 定期券は必要だから毎月何気なく買っているけど、そもそも得する買い方ってあるの?
- 何日以上使うと定期券の方がお得なのか知りたい
- 定期券を買うのにお得なクレジットカードは何?
毎日会社に通っているサラリーマンやOLにとって、このようなこと一度は考えたことはあるのではないでしょうか?
交通費が支給される会社が多いとはいえ、毎月万単位の支払いなのでできれば少しでもお得に買いたいですよね。
そこで本記事では、通勤定期券を数倍お得に買う方法や、定期券購入で高いポイントが得られるトクするクレジットカードついて詳しく解説しています。
この記事を読むことで、自分はどのような方法で買えば一番得なのか、定期券の元を取るには何日以上利用すればよいのか詳しい詳細がわかります。
通勤定期で得したいと思っている方は、ぜひ最後までこの記事をチェックしてみてください。
目次
通勤定期のお得に買うための方法6選

①クレジットカードで買う
通勤定期を買う場合、現金ではなくクレジットカードを使うようにしましょう。
何故なら、現金払いでは一切ポイントが付きませんが、クレジットカードであればカード利用によるポイントが付与されるからです。
仮に1%還元のクレジットカードで定期券を購入した場合、↓これだけのポイントが獲得できます。
年間でランチ2回分くらいのポイントにはなるので、バカにはできません。
【月13,000円の定期券を購入した場合の例】
- クレジットカード(1%還元)
⇨ 13,000円×1%=毎月130ポイント(年間1,560ポイント) - 現金
⇨ ポイント還元なし
モバイルSuicaやモバイルPASMO定期券の場合、カードタイプと違い、ポイント対象外となるクレジットカードもあります。モバイルを利用している方はお持ちのカードがポイント付与の対象かどうかよく確認しましょう。
②6ヶ月の定期を選ぶ
1ヶ月より3ヶ月、3ヶ月より6ヶ月定期を選べば割引率が一番高くお得です。
中には6ヶ月ごとに定期代が支給され、6ヶ月定期券を買うように指定する会社もあるかもしれません。
毎月定期代として交通費が支給されているのであれば、なるべく有効期限が長いものを選ぶようにしましょう。
特に6ヶ月定期券は割引率が最も高いため、おすすめです。
【三鷹〜新宿まで定期券を購入した場合の例】
- 1ヶ月定期券 ⇨ 6,950円
- 3ヶ月定期券 ⇨ 1,9810円(1ヶ月定期券と比べ1,040円お得)
- 6ヶ月定期券 ⇨ 3,3480円(1ヶ月定期券と比べ8,220円お得 3ヶ月定期券と比べ6,140円お得)
③最もお得な経路を選択
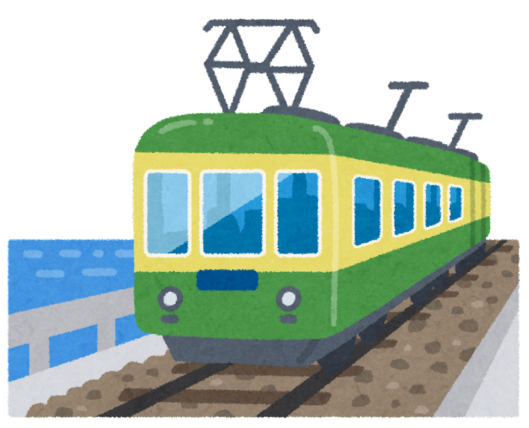 自宅の最寄り駅から目的地の会社の最寄り駅まで、複数の経路がある場合です。
自宅の最寄り駅から目的地の会社の最寄り駅まで、複数の経路がある場合です。
通勤時間があまり変わらないのであれば、最も安い経路で購入すると定期代を節約できます。
最も安い経路以外にも、途中プライベートでよく利用する駅を経路にすることにより、結果安くなる可能性があります。
プライベートでよく利用する駅はあるか、もし利用しないならどの経路が一番安いか、考えて選択すると節約に繋がります。
モバイルSuica定期券であれば、購入時に自動的に複数の経路が候補で出てくるので、料金を比較してみてください。
④1つ2つ先の駅まで買う
通勤定期は、1つ先、2つ先の駅まで買っても同一料金の場合があります。
【例】
- 西荻窪~新宿 6ヶ月定期券33,480円
- 三鷹~新宿 6ヶ月定期券33,480円
2つ先の三鷹から購入しても料金は全く変わりません。使う機会がなかったとしても、できれば2つ先の駅まで買っておくことをおすすめします。
もしかしたらプライベートなどで乗り越し精算することもあるかもしれません。万が一使わなかったとしても料金は全く一緒なので損することはないでしょう。
⑤モバイルにする
 まだICタイプの定期券や磁気定期券を使われている方は多いですが、特にJR東日本エリアの方であればモバイルSuica定期券の利用が圧倒的にお得です。
まだICタイプの定期券や磁気定期券を使われている方は多いですが、特にJR東日本エリアの方であればモバイルSuica定期券の利用が圧倒的にお得です。
JREポイントに登録することにより、JR東日本エリアの乗車ならモバイルSuica利用で50円ごとに1ポイント付与されます。(還元率2%)
これは定期券でも通常の乗車でも付与されます。
例:【毎月13,000円の定期券を購入で】
- 1ヶ月 ⇒ 260ポイント
- 6ヶ月 ⇒ 1,560ポイント
- 12か月 ⇒ 3,120ポイント
ちなみにカード型の場合は、定期券購入によるポイント付与はなく、通常の乗車で200円ごとに1ポイントのみです。(0.5%還元)
利用するのであればモバイルSuicaが圧倒的にお得!
⑥オフピーク定期券を購入する(JR東日本エリア)
混雑する平日朝の時間帯は利用できませんが、それ以外の時間帯であれば通常通り定期券として利用できます。
通常の通勤定期と比べ約15%も安く購入できます。例えばシフト制や出勤時間が遅い方など、平日朝の時間帯に通勤される方はこちらも検討してみましょう。
ピーク時間帯の判定は自動改札機の入場時に判定され、駅によりピーク時間帯は異なります。
さらにお得に定期券を買う方法

Suica定期券編
JREポイントに登録する
お持ちのSuica(モバイル・カード)をJRE POINT WEBサイトに登録すると、モバイルSuica定期券の購入やJRの在来線乗車などでJREポイントが貯まります。
- モバイルSuica定期券購入、在来線乗車 ⇒ 50円につき1ポイント
- カード型で在来線購入 ⇒ 200円につき1ポイント
定期券の購入でポイントが付与されるのはモバイルSuica定期券のみですが、一度登録すればずっと有効のため毎回余計な手間はかかりません。
ビューカードで買う
ビューカードはJR東日本グループのクレジットカードです。(株式会社ビューカードが発行)
ビューカードであればどのカードも対象で、モバイルSuica定期券購入で3%ものポイントが付きます。
【ビューカードの種類】
- ビュー・スイカカード
- ビューカード ゴールド
- JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード
- JRE CARD
- ビックカメラSuicaカード
- イオンSuicaカード など
ビューカード ゴールド、JALカードSuica CLUB-Aゴールドカードで購入した場合は4%還元になります。
PASMO定期券編

各社の乗車ポイントのサービスに登録する
PASMOでもJR東日本エリアのJREポイントのように乗車する度にポイントが付与されるサービスを展開している鉄道会社があります。
【例】
- 東京メトロ ⇒ メトポ(会員ランクに応じて利用額の2~10%還元
- 西武鉄道 ⇒ SEIBU Smile POINT(オフピーク通勤で10ポイント)
よく利用する鉄道会社に乗車する度にポイントがもらえるサービスがないか確認し、あれば利用するとお得です。
鉄道会社提携のカードや高還元率カードを使う
SuicaはJR東日本の交通系ICカードですが、PASMOは株式会社パスモが発行しているものの、主に関東地方を中心とした私鉄やバス事業者が発売する交通系ICカードです。
ビューカードのように「これ1枚で全ての私鉄利用がお得」というものがありません。
例えば、下記のようなそれぞれの鉄道利用に適したクレカがあります。
- 西武鉄道 ⇒ 「SEIBU PRINCE CLUBカード セゾン」
- 東京メトロ ⇒ 「To Me CARD Prime」
- 小田急電鉄 ⇒ 「OPクレジット」
ご自身がどの鉄道をよく利用するか、よく調べてから選ぶとよいでしょう。
鉄道利用に適したカードを見つけるのが難しい場合、一般の高還元率クレジットカードで購入するのが簡単でお得です。
定期券購入におすすめのクレジットカード
 基本的に年会費が無料(一部有料も含む)で、モバイルSuica、モバイルPASMO定期券購入に高還元率になるカードを紹介します。
基本的に年会費が無料(一部有料も含む)で、モバイルSuica、モバイルPASMO定期券購入に高還元率になるカードを紹介します。
ビックカメラSuicaカード【モバイルSuica】
JR東日本グループのビューカードとビックカメラが提携しているクレジットカードです。
おすすめできる特長は下記の通りです。
- モバイルSuica定期券購入で3%還元
- オートチャージやモバイルSuicaチャージで1.5%還元(普段の電車利用や買い物もお得)
- 年会費初年度無料で、2年目以降も1度利用で無料(通常は524円)
- その他の利用でも1%還元(JREポイント0.5%+ビックポイント0.5%)
改悪されるリスクも小さく、安定して高還元率を得られるのでモバイルSuicaユーザーにはおすすめの1枚。
数あるビューカードの中でも、年会費実質無料で利用できるのはビックカメラSuicaカードだけです。
Vポイントカード Prime【モバイルSuica・モバイルPASMO】
※2025年3月31日を持って新規受付は終了しています。
Vポイントカード Prime(旧:Tカードprime)は、Vポイントが貯まる基本還元率1%のジャックスが発行するクレジットカードです。
大きな特長は、日曜日利用は200円につき3ポイント(1.5%還元)になること。
日曜日にモバイルSuica、モバイルPASMOの定期券購入を購入すれば、1.5%の高還元率が得られます。
基本還元率も1%と高く、その他の電子マネーチャージへの利用など定期券購入以外にも使い道は多いため、持っていて損はない1枚です。
リクルートカード(VISA・Mastercard)【モバイルSuica・モバイルPASMO】
 リクルートと三菱UFJニコスが提携しているクレジットカードで、どこで使っても1.2%という高還元率。
リクルートと三菱UFJニコスが提携しているクレジットカードで、どこで使っても1.2%という高還元率。
年会費は無料でモバイルSuica定期券でも1.2%付くので、こちらもおすすめです。(JCBブランドは0.75%還元)
ただし、モバイルSuicaチャージでポイントが付くのは月3万円までと公式サイトに記載があります。
モバイルSuica定期券購入でも3万円以上はポイント付与されるかどうかは未確認のため、利用する場合はしっかり確認しましょう。
ANA Pay【モバイルSuica・モバイルPASMO】
こちらはクレジットカードではなく、ANAが発行しているスマホ決済用のアプリです。
ANA Payに登録をするとANA Pay専用のバーチャルプリペイドカード(VISA)が発行されます。カード番号を使ってオンラインで利用できます。(200円ごとに1マイルが貯まる)
お持ちのクレジットカードからチャージして、チャージしたANA Payのプリペイドカードを使ってモバイルSuica定期券を購入すれば、クレカポイント+マイルの2重取り可能!
【例】クレカからANA PayへチャージしてモバイルSuica定期券を買う
- クレカからANA Payへチャージ +0.5~1.5%
- ANA PayのバーチャルカードでモバイルSuica定期券を購入 +0.5%
合計1~2%還元
【参考】1ヶ月の通勤定期券なら、16~20日以上利用するとお得!
定期券を買った方が良いのか、それとも買わずにSuicaなどで支払った方が良いのか、それは利用する鉄道会社・利用期間・距離などで異なります。
ここでは1ヶ月定期券を買った場合と比較して、何日以上利用したら得になるのか、比較表を作ったので参考にしてください。
※「〇日間利用」は、交通系ICカードで支払った往復運賃を利用日数でかけた金額です。2025年4月1日現在の運賃。
| 鉄道会社名 (通勤経路) |
1ヶ月定期 | 16日間利用 | 18日間利用 | 19日間利用 | 20日間利用 |
| JR東日本 (三鷹~新宿) |
6,950円 | 7,360円 | 8,280円 | 8,740円 | 9,200円 |
| 京王電鉄 (府中~初台) |
11,760円 | 10,048円 | 11,304円 | 11,932円 | 12,560円 |
| 西武鉄道 (所沢~池袋) |
13,580円 | 11,392円 | 12,816円 | 13,528円 | 14,240円 |
| 東京メトロ (千川~月島) |
8,970円 | 8,064円 | 9,072円 | 9,576円 | 100,80円 |
16~20日間利用すると通勤定期を買う方がお得になります。
お得になる日数は鉄道会社によって異なり、JR東日本では1ヶ月で16日間以上利用するのであれば通勤定期が得になります。
一方で西武鉄道では20日以上利用しないとSuicaやPASMOなどの交通系ICカードを利用した方が安くなる結果になりました。
ご自身の1ヶ月の通勤日数と比べてお得な方を選びましょう。
まとめ:クレカ払い・モバイル・6ヶ月がおすすめ!
 今回は、通勤定期のお得な買い方について解説しました。
今回は、通勤定期のお得な買い方について解説しました。
現金払いを辞めクレジットカードで買う、毎月ではなく6ヶ月定期を買う、カード型ではなくモバイルにする、これだけでも年間数千〜数万ポイントの差が出るので通勤定期の買い方は非常に重要です。
以下の記事では、通勤定期におすすめのモバイルSuicaの還元率を最大4重取りする方法について解説しているので、こちらの記事をぜひ合わせて読んでみてください。

・通勤定期はクレカ払いで、モバイル、6ヶ月がお得
・最もお得な経路を選択し、同一料金なら1つ2つ先の駅まで買う
・SuicaならJREポイントに登録して、ビューカード購入がお得
・PASMOなら乗車ポイントサービスに登録、よく利用する鉄道会社提携のカードや高還元率カードがおすすめ
・ビックカメラSuicaカードなら年会費無料で利用できる唯一のビューカード